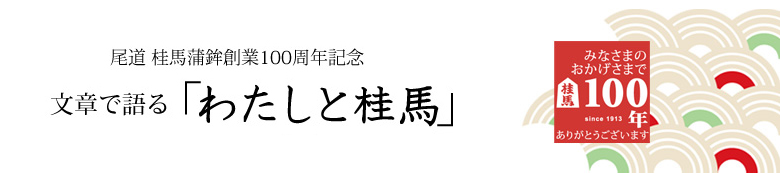|
私にとって“桂馬”とは尾道であり、尾道とは父である。
父は大正末年、尾道の対岸 向島で生まれ、戦後上京し、縁あって呉出身の母と所帯を持った。
私はその長男として埼玉に育ち、事後今日に至る。
私自身尾道で暮らしたことはなかったが、放浪記を熱愛していたことも有り、尾道はその佇まいと共に私の秘かな誇りであった。
また父の故郷と言うだけでなく、母方の祖父が尾道の女学校に封職していた時期もあり、我が家にとって尾道は特別な街であった。
そんな我が家で尾道と言えば浮かんで来るのが“桂馬”である。
家族で帰郷の折、前後することはあってもその式次第は決まっていた。
尾道の駅に降り立ち、明るい太陽と潮の香、それに愛すべき尾道弁を全身に浴びると、駅前にあった立ち食いのうどん屋に入り
肉うどんを食べる。(当時の尾道は朱華園はあったものの、まだラーメンに席巻されてはいなかった)
初めて食べた時、関東育ちの私はその味に仰天した。
美味であった。子供心に尾道というところはスゴイところだと思う。
時には海岸通りの定食屋(?)へ入る。ひと皿ごとに盛られたお菜を自分で選んでテーブルに運ぶ。
煮魚はオバサンが"チン"してくれる。父が美味しそうにビールのグラスをかたむける。
三角のおいなりさんに初めて出会い(関東は俵型)、オデンに肉が入っているのにこれまた仰天した。(今思えば牛スジである)
ウマヅラの煮付けを食べていて、何かが刺さった。釣針だった。ワイルドさに感動した。いよいよ尾道はスゴイ。
(この歳になって痛感するが、今は無き海岸通りの定食屋は飲んべえにとって最高の場所ではなかったろうか?!実に残念である。)
そしていよいよ帰郷前半のメインイベントが始まる。
本通りへ向う。団地住いの私にはアーケード街自体がめずらしく、乳母車(?)に盤台(?)をのせて魚をさばくオバサン達に目を見はる。
生きたシャコを初めて見た。口を開けて縄でつながっているデベラがのれんの様で妙におかしい。
そのうち将棋の駒が見えてくる。“桂馬”である。
我が家の尾道着は大概午後であったからもうカマボコはほとんど残っていない。売切れ御免である。その為帰郷前に予約しておいたものを受け取りに行くのである。
いやが上にも有難さが増す。ただし昨今見聞きする名店としての気取りや傲慢さは微塵も感じられず、店の方々の丁寧な受け答えに
仕事に対する真剣さの表われであることは子供ながらに理解できる。
そもそも向島の実家へ尾道のカマボコを土産として持っていく事自体、考え様によっては妙である。
しかし誰ひとりそれを変だとは思わない。父は恭しく経木の箱を受け取り、生家へ戻ると喜々としてそれを取り出す。
当時父の生家を継いでいた叔父がそれを押し頂く。こうして我が家の帰郷の儀式が一段落する。
だがこれだけでは終わらない。
夕餉の膳には当然“桂馬”が所狭しと並ぶ。
板カマ、豆チク、柿、梅、駒、ごぼう天とそれこそ桂馬尽しであるが、しかしこれは父の持参した土産の折ではなく、
叔父がわざわざ水道を渡り買って来たものなのである。
父は叔父が“桂馬”を買って待っているのを知っている。
叔父もまた父が“桂馬”を持参することは百も承知である。それでも毎回これが続く。
ハレの日の食膳に欠かせないのが“桂馬”であり、また久々の再開を互いの好物で祝いたい家族の愛である。
話がはずむ。盃が回る。皆が笑っている。“桂馬”をかこんで笑っている。
かくして“桂馬”なくして我が家の帰郷は有り得ない。
帰京の日も“桂馬”との関わりは続く。
叔父は必ず土産として“桂馬”を持たせてくれる。
さらに東京行きの列車の時刻までの寸刻を惜んで、父が“桂馬”にかけつける。
帰郷当日に予約しておいた帰りの土産を受け取りに行くのである。
こうして網棚には2個ないし3個の折り詰めが仲良く並ぶこととなる。
当時新幹線はまだ大阪までで、東京〜広島間の寝台急行も健在だった。そんな在来線の車中で“桂馬”の折りのフタを開け
風を送っていた父の姿が今でも目に浮かぶ。列車の冷房も完備されておらず、
新幹線は冷房がききすぎると夏でもセーター持参で乗り込んだ時代、保冷容器やクール便などは夢のまた夢、かつ“桂馬”は
天然素材の鮮魚扱い、そもそも東京に持って帰ること自体がある種掟破りの感さえあったが、それを承知でどうにか保たそうと、
必死(?)であおいでいたのであった。
こうした努力の結果、どうにか我が家へたどり着いた“桂馬”も、“汗をかく”と言って大急ぎで食べてしまうのが常であった。
それなら帰りの車中で少しはつまんでしまえばいいものを(父は必ず車中で“飲んで”いたから)と思ったが
私の記憶の中に車中で“桂馬”をパクつく父の姿は無い。そんな事は恐れ多いとでも考えていたのだろうか?
こんな経験が、私の中に単なる食べ物や名産品と言ったものを越えた“桂馬”という言葉の持つ魔力のようなものを育んでいったのである。
こうした“桂馬”の魔力は何も我が家に限ったことではなく、尾道近辺、いや広島県民の少なからぬ人々が感じられていることとは思うが、
呉にある母方の実家もその例外ではなかった。
母方の祖父は尾道に赴任した経験も有り、“桂馬”は当然知っていたが、年に数度の上京の際は常に自分の晩酌用の賀茂鶴と、
状況が許す限り“桂馬”をさげて来た。私の記憶にある母の実家への里帰りにも、その膳にはよく“桂馬”が並んでいた。
帰りには父の生家同様土産に持たせてくれたことも度々有った。
当時はおそらく本店のみの営業であったからわざわざ尾道まで出向いたものであろう。
父の生家との往来も有ったが、その際の土産や持ち帰り用の折りの数を相談している光景も目に残っている。
“桂馬”の令名は尾道近在に止まらない。
“桂馬”の味については、私のような門外漢が云々する必要はないであろう。
関東にはない独特な歯ごたえと噛めば噛む程滋味の広がる上品さが無類のものであることは百年の歳月が物語っている。
またその美しさにも誰もが頷くことと思う。
梅、柿、駒、豆チク等々その愛らしい形は決して嫌味のない控え目な意匠であり、板や焼、特に私が好きな柿のつややかながら
しっとりとした色合いは絶品である。
柿と言えば私の記憶では以前は本物の柿のヘタを使っていたように思う。豆チクの竹で父は笛を造ってくれた。
素材は元より、こうした美しさと自然を感じさせる一品一品が私の中の“桂馬”の魔力をいやが上にも強くして来たことは間違いない。
私が二十歳の時、父が他界した。
突然の事であり、その死の本当の意味をどこまで理解出来ていたかは難問だが、若いが由の甘い感傷に浸った事は事実である。
そんな時期、ひとりで尾道を訪れたことがある。
大正生まれの戦中派、子供の前では寡黙だった父の何かを掴みたかったのかも知れない。
駅に降り立ち“桂馬”に向った。
父にとっては故郷のやすらぎを感じる親しみのある場所だったのかもしれないが、私にとっては一種の“聖地”であった。
もちろんひとりで訪れたことはない。
胸が高鳴り、極度に緊張していた。二・三度店の前を往き来した後、勇を鼓してひんやりとした店内に入った。
そして柿とごぼう天をひとつずつ購ない、缶ビールと共に渡船に乗った。
渡船で渡る尾道水道はまぶしいくらいに明るかった。
向島の緑が美しく、尾道の寺々の屋根が清かに佇んでいた。
その日渡船で何往復したであろう。
対岸の農家に生まれ、早くして父を亡くし、母を支えて苦労しながら中学へ通った日々。青雲の志と絶望的な戦況と後に残す母への
想いを共に胸に抱きながら軍の学校へ旅立った日、そして戦い敗れ自暴自棄となりながらも一縷の望みを託して上京した日、
亡父が何千回となく乗ったであろう渡船にほんの一刻でも身を委ねていたかった。何かを感じ取りたかった。
私の手には“桂馬”があった。不謹慎にも缶ビールさえ手にしていた。しかし父の手には何もなかったはずである。
ふっと新藤監督の「裸の島」が頭に浮かんだ。
小島の農家の次男坊にとって対岸の尾道は輝くような都会であったに違いない。
大げさではなく文明の玄関口にも思えたであろう。
そのまぶしいばかりのあこがれの中に、老舗としての“桂馬”の味があったのではなかろうか。
「うどんは馳走」と言っていた農家に“桂馬”はめったに口に出来るものではなかったはずである。
何かの折りに食すことの出来た“桂馬”の味は、どれほど美味に感じられたであろう。
多くの人々にとって“桂馬”は決して日々の“お菜”ではなく、ハレの日の“御馳走”だったに違いない。
であればこそよその人間が尾道への土産に尾道の“桂馬”を持っていくことへ何の疑問も違和感も感じないのではなかろうか。
ここまで人の心を捕える力を魔力と呼ばずして何であろう。
そしてこの魔力を支えているのが百年に渡る“桂馬”の方々の努力と精進と愛情の賜と信じて疑わない。
今や“桂馬”は全国区である。マスコミにも度々紹介され全国の百貨店の名店会でも常に目玉のひとつである。
宅急便で居ながらにして味わうことも出来る。
若い後継者もますます精進され、伝統とアイデアを融合された素張しい品々を送り出されている。
まさに名店の名店、老舗の中の老舗であり尾道の誇り、広島の宝である。
グルメブームの中、ますます多くの人々に愛され、その食卓を飾っていくことだろう。
しかしながら“桂馬”という言葉に父のように特別な想いを感じる人が少なからずいたことを忘れないでいてほしい。
それはあこがれであり、輝きであり、またなつかしさである。誇らしさであり、はにかみであり、神々しさでもある。
若い日に渡船の上で感じた父の“桂馬”を愛する気持ちが本当にこんなものだったかどうか、今は知るすべもない。
が、ほんの少し父に近づけた思いがしたのは事実である。
これも“桂馬”の魔力だろうか?いやそう信じている。
私にとって父は尾道であり、尾道は“桂馬”である。
私もそろそろ父の享年に近づいて来たが、父から授かった“桂馬”の魔力をこれからも感じ続けていたいと思っている。
|